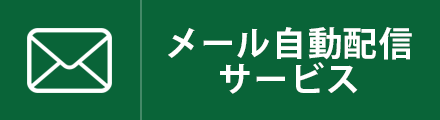評価調査
- 国際協力事業
- 評価調査
FASIDはこれまでODA事業の質の向上を目指して様々な評価調査や評価手法の研究を行ってきました。これらの知見を活用して、民間企業の財務諸表に反映されない事業の効果を評価する手法の検討なども行っています。
令和6年度ODA評価「新型コロナウイルス感染症対策支援の評価」

| 全世界 | |
| 2024年6月~2025年3月 | |
| 外務省 | |
| 新型コロナウイルス感染症への対応においては、日本は「誰の健康も取り残さない」を理念として、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(注)の達成を目指し、世界100カ国を超える国に対して、二国間協力や国際機関を通じて幅広い支援を実施しました。当財団は、2019~2023年度の日本のODAによる新型コロナウイルス対策支援について包括的な評価を行い、感染症対策を含むグローバルヘルス分野における協力に関して、今後に活かせる提言や教訓を得ることを目的として本評価を実施しました。また、評価結果を公表し、国民への説明責任を果たすことも重要な目的の一つとしています。本評価の対象は、全世界を対象とした支援であり、ケース・スタディ国としてマラウイとベトナムを選定し、現地調査を実施しました。 (注)ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ:すべての人が、適切な健康増進、予防・治療・機能回復に関するサービスを、支払い可能な費用で受けられること。 |
【参考】(外部サイト)
コロンビア国平和構築に資する包摂性を確保した農業農村開発事業強化プロジェクト中間レビュー調査(評価分析)(単独型)
| コロンビア/評価・平和構築・農村開発 | |
| 2024年2月~2024年4月 | |
| 独立行政法人 国際開発機構(JICA) | |
| コロンビアでは、半世紀以上にわたり武力紛争が続き、800万人ともいわれる国内避難民が発生していましたが、2016年に政府と革命軍との間で歴史的な和平合意が締結されました。和平合意の第一の柱である「総合的農村開発」は、紛争の主要な要因とされた都市部と地方農村部の経済格差の是正を目指していますが、遅々として進んでいません。本プロジェクトは、コロンビア国内の紛争影響地域において、包摂性を確保した農村開発事業を行うことにより、農業開発庁の組織能力の強化を図り、もっと和平合意の履行を促進することを目的としています(2021年11月~2026年11月)。 当財団は、本プロジェクトの中間点において、プロジェクト前半の活動の実績、成果と課題を確認し、残りの期間に向けた提言を取りまとめることを目的として、中間レビュー調査を実施しました。本プロジェクトの評価にあたってはDAC6項目評価に加えて、紛争影響地域における事業評価の視点による分析を行いました。 |
キューバ国「基礎穀物のための農業普及システム強化プロジェクト終了時評価調査」(評価分析)(単独型)

| キューバ/評価・農業 | |
| 2022年6月~2022年8月 | |
| 独立行政法人 国際開発機構(JICA) | |
| キューバは食糧消費量の多くを輸入に依存しています。同国政府は食糧安全保障の観点から、食糧輸入量の減少を目指し、国内の食糧、特に基礎穀物の生産を強化するために、様々な施策を実施してきました(集団による大規模農業生産から個人農家や共同組合単位による小規模生産への移行、新規就農者への未利用農地の無償貸与等)。しかしながら、期待する穀物の増産には結びついていませんでした。このような課題に対しJICAは、農業普及関係者と関連機関の普及能力強化、普及ツール・教材の整備、及び普及人材育成の仕組みの構築を通じて、基礎穀物生産農家に対する栽培技術の普及体制の強化を目指した「基礎穀物のための農業普及システム強化プロジェクト」(2017年1月~2022年7月)を実施しました。 当財団では、事業完了を間近に控えた時期に、活動の実績・成果を評価し、提言・教訓を抽出することを目的として終了時評価調査を担当しました。 |
令和4年度ODA評価「トルコ国別評価」調査業務

| トルコ/評価 | |
| 2022年4月~2023年2月 | |
| 外務省 | |
| 日本は対トルコ国別開発協力方針に基づき、①「経済を支える強靭な社会基盤づくりへの支援」、②「民間セクターとの連携強化」、③「開発パートナーとしての連携強化」、④「シリア難民対策への支援」の4つの重点分野において協力を進めています。本評価業務は、2017年度から2021年度の5年間における日本のトルコに対する援助政策及び同政策に基づく支援を評価対象として、トルコへの支援実績に対する総合的な評価を行い、有益な提言を抽出することを目的として実施されました。 当財団は、評価主任・アドバイザーの監督の下、1. 開発の視点からの評価(①政策の妥当性、②結果の有効性、③プロセスの適切性)と、2. 外交の視点からの評価について、国内調査と現地調査で得られた情報を分析し、外務省関係各課・室、日本大使館、JICA関係者などと3回の検討会を開催しました。そこで調査進捗を共有しながら関係者のコメント・意見を聴取し、これらを踏まえて2023年度に改定が予定されている対トルコ国別開発協力方針の策定に向けた提言の抽出を行いました。 |
【参考】(外部サイト)
【過去に実施したODA国別評価の報告書】(外部サイト)
開発金融機関における開発効果測定手法に関する調査
| 全世界/評価・金融 | |
| 2021年6月~2022年1月 | |
| 独立行政法人 国際協力機構(JICA) | |
| 事業や活動の結果として生じる社会的インパクトの実現を目指した民間向け投融資を実施している組織では、財務的リターンと社会的リターンの両方を追求しています。これまで定量的な測定が難しいとされてきた社会的リターンについても、近年では、国際開発金融機関(MDBs)や二国間開発金融機関(DFIs)において、個別案件レベルのみならず、投融資案件全体の測定手法の開発・導入が進んでいます。 本調査は、他の開発金融機関における開発効果測定手法等の取り組みを参考に、JICAが民間活動支援を通じた経済協力を行う海外投融資事業において、投融資案件全体の開発効果測定が可能となるような手法の導入を検討することを目的に実施されました。 まず主要な開発金融機関として、国際金融公社(IFC)、米州投資公社(IDB Invest)、欧州投資銀行(EIB)欧州復興開発銀行(EBRD)等のMDBs、ドイツ投資公社(DEG)、米国国際開発金融公社(DFC)、カナダ開発基金(FinDev Canada)フィンランド産業協力基金(Finnfund)、オランダ開発金融公庫(FMO)、英国連邦開発公社(CDC)、フランス経済協力振興投資公社(PROPARCO)等のDFIsにおける開発効果測定の取り組みを調査し、これらを参考に、JICA海外投融資における開発効果測定のための評価軸の検討を行いました。さらに、JICAの海外投融資に適し、かつ投融資案件全体の開発効果測定が可能な評価項目・配点・評価方法を検討し、パイロット評価の実施を経て、ツールと手順書を作成し、運用体制の提案を行いました。 |
過去のODA評価案件(国別評価)のレビューと国別評価の手法に関する調査研究
| 全世界/評価 | |
| 2020年10月~2021年3月 | |
| 独立行政法人 国際協力機構(JICA) | |
| 外務省では毎年、ODAの政策評価を実施しています。ODA政策評価は外部に委託され、第三者評価の形式で実施されています。本調査研究では、2005年から2019年に実施されたOD政策評価のうち国別評価56件について、提言・教訓のレビュー、類型化、さらにODA政策に有用な教訓の抽出を行いました。また、レーティングが行われた13件の評価について、評価枠組みを分析し、国別評価における評価枠組みの再考を行いました。 この分析を通じて、サブレーティングの基準の明確化や検証項目の明確化の必要性について提言を行いました。また、国別評価の実施時期を国別開発協力方針改定のタイミングに合わせることにより、PDCAサイクル強化につながる点についても提言しました。 |
【参考】(外部サイト)
外部事後評価:モンゴル「ツェツィー風力発電事業」(海外投融資)

| モンゴル/評価 | |
| 2018年12月~2020年1月 | |
| 独立行政法人 国際協力機構(JICA) | |
| モンゴルでは、経済成長や都市化に伴い電力需要が増加し、不足分は中国やロシアから輸入しています。また国内の発電量の96%は石炭火力によるもので、政府はエネルギー源の多様化を目指し、再生可能エネルギーの導入を促進しています。 ツェツィー風力発電事業は、50メガワットの風力発電所の建設・運営により、南ゴビ地域の豊富な風力資源を活用し、国家の電力網に供給して需給の安定性を改善することを目的に、モンゴル企業のNewcom社とソフトバンクグループのSBエナジー株式会社がモンゴルに設立した特別目的会社Clean Energy Asia LLCによって実施されました。JICAは、欧州復興開発銀行(EBRD)との協調融資を通じて、この事業を支援しました。 本事業は海外投融資であるため、その評価にあたっては、国際金融公社(IFC)が使用しているステークホルダー分析を参考にし、DAC5項目に加えて、JICAの役割や貢献、金融面における付加価値の生成についても分析を行いました。 |
UN Women プロジェクトの中間評価・終了時評価「若年層のジェンダー平等意識向上のための啓発事業」
| 日本/評価・ジェンダー | |
| 中間評価:2019年4月~2019年7月 終了時評価:2020年2月~2020年4月 |
|
| UN Women(国連女性機関) | |
| 世界経済フォーラムが公表する「グローバルジェンダーギャップレポート」によると、日本のジェンダーギャップ指数の順位は153か国中121位(2019年)と低く、日本のジェンダー格差は他国に比べて著しいことを示しています。日本社会のあらゆるレベルにおいて、ジェンダー平等を推進することが喫緊の課題です。 このような日本の状況に鑑み、若者が持つ可能性とジェンダー関係の社会変革に着目して、UN Women(国連女性機関)は、資生堂株式会社の支援を受け、2017年4月から2020年3月まで、若者のジェンダー平等意識を啓発するアドボカシーと能力強化のプロジェクトを日本で実施し、その中間評価および終了時評価を当財団が受託しました。 本評価は、調査結果から教訓・提言を導き出すことによって、UN Womenの今後の事業を改善するとともに、日本国政府やドナーに評価結果をフィードバックすることで説明責任を果たし、組織として学びを得ることを目的として実施されました。 中間評価時には、プロジェクトを5つの評価項目(妥当性、有効性、インパクト、効率性、持続性)に沿って評価しました。終了時評価では、国連評価グループ(UNEG)およびUN Womenの評価ガイドラインに則り、妥当性、有効性、効率性、持続性、およびジェンダー平等・人権の5項目に沿って評価し、評価の着眼点やプロセスにおいては、ジェンダー平等と人権原則の統合に重きを置きました。 |
【参考】(外部サイト)
2015年度 案件別外部事後評価「日本人材開発センター8案件および総合的分析」

| ベトナム、カンボジア、モンゴル、キルギス、ラオス、ウズベキスタン、カザフスタン、ウクライナ | |
| 2016年10月~2017年3月 | |
| 独立行政法人 国際開発機構(JICA) | |
| 「日本人材開発センター(以下、日本センター)」は、中央アジアや東南アジアの市場経済移行国への「顔の見える援助」として、ビジネス人材の育成と日本との人材交流の強化を目的に1998年から開始されました。事業の枠組みは、①ビジネス人材の育成、②日本語コース、③相互理解促進事業、と全ての国で同じながらも(一部の国では無償資金協力による拠点施設の整備も行われました)、各国の置かれた状況により具体的な事業内容や発展プロセスは異なり、現在では各センター特徴ある事業が展開されています。 本調査では、8ヶ所(ベトナム、カンボジア、モンゴル、キルギス、ラオス、ウズベキスタン、カザフスタン、ウクライナ)の日本センターについて、センター毎の事業の成果やインパクト、また実施体制などを評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性)の観点で評価すると同時に、各センターを取り巻く環境に留意しながら、各センターの評価結果を横断的に比較検討し、日本センター案件の今後の計画作りや運営管理方法の改善に向けた教訓・提言の抽出を行いました。 |
【参考】(外部サイト)
テーマ別評価「JICA協力プログラムの評価可能性向上に向けた分析」
| 全世界・タンザニア/評価 | |
| 2014年6月~2015年2月 | |
| 独立行政法人 国際協力機構(JICA) | |
| JICAは、1999年に初めて「協力プログラム」の考え方を導入し、それまでプロジェクト単位で実施してきた事業を組み合わせて、開発のインパクトを最大化することを目指しました。以来、開発効果を向上させるための最適な事業運営形態として、プログラムの実施が推進されています。他方で、プログラムの中には、個々の案件相互の関係への配慮が必ずしも十分でなく類似性のみから協力プログラムとしてまとめられているケースがあり、開発効果の発現を目的とする協力プログラムとしての意義が不明確なものもあります。プログラム評価実施の観点からも、プログラム形成時の適切なデザインや評価可能性の向上が課題とされていました。 そこで、JICA協力プログラムの形成と評価をレビューし、協力プログラムの形成と評価に必要なツール/様式案を作成し、タンザニア「コメ生産能力強化プログラム」をはじめとする5つのプログラムにおいてトライアルを行った上で、協力プログラムの分類を行い、プログラムのタイプに応じたモニタリング・評価案を提言しました。 |
【参考】(外部サイト)
2013年度「社会性評価基準の国際標準化に向けた戦略の研究」
2014年度「社会性評価基準の国際標準化研究」フェーズII
| 日本・全世界/評価・市民参加 | |
| 2013年5月~2014年3月 2014年6月~2015年3月 |
|
| 外務省 | |
| 近年、開発資金としての社会的投資が注目されると同時に、投資が生み出す社会的リターンの評価基準・フレームワークをめぐる議論が活発化しています。 2013年度「社会性評価基準の国際標準化に向けた戦略の研究」 では、社会的インパクト評価基準に関する動向を調査した上で、社会的インパクト評価基準の標準化において日本が取りうる戦略の検討を行いました。 2014年度「社会性評価基準の国際標準化研究」フェーズII では、英国と日本における社会的インパクト評価の現状を分析し、世界各国の7つの評価ガイドラインを分析し評価において必要不可欠な要素を抽出しました。その上で日本における社会的インパクト評価促進のための仕組みづくりに関する諸外国の経験や日本の現状を調査し、日本における社会的インパクト評価促進のための環境整備の方策を考察しました。 担い手の活動が生み出す「社会的価値」を「可視化」し、これを「検証」し、資金等の提供者への説明責任(アカウンタビリティ)につなげていくとともに、評価の実施により組織内部で戦略と結果が共有され、事業・組織に対する理解を深め組織の運営力強化に資するような評価基準を考察しました。 |
【参考】
案件別外部事後評価

| 全世界/全分野 | |
| 独立行政法人 国際開発機構(JICA) | |
JICAは説明責任と業務改善を目的として事後評価を実施しています。事後評価業務では、資料レビューや関係者への質問票・インタビューを通じて情報を収集し、DAC評価6項目に基づいて評価を行っています。対象地域はアジア、アフリカ、中南米、対象分野は民間セクター、教育、運輸交通、自然環境保全、保健医療、水資源・防災と幅広く、評価分析を行っています。当財団は毎年度、事後評価業務を受注しており、過去10年間(2015~2024年)の受注実績は以下のとおりです。
|